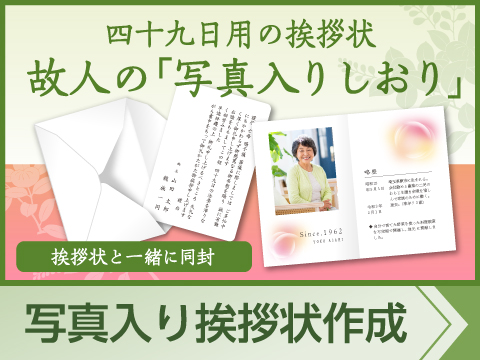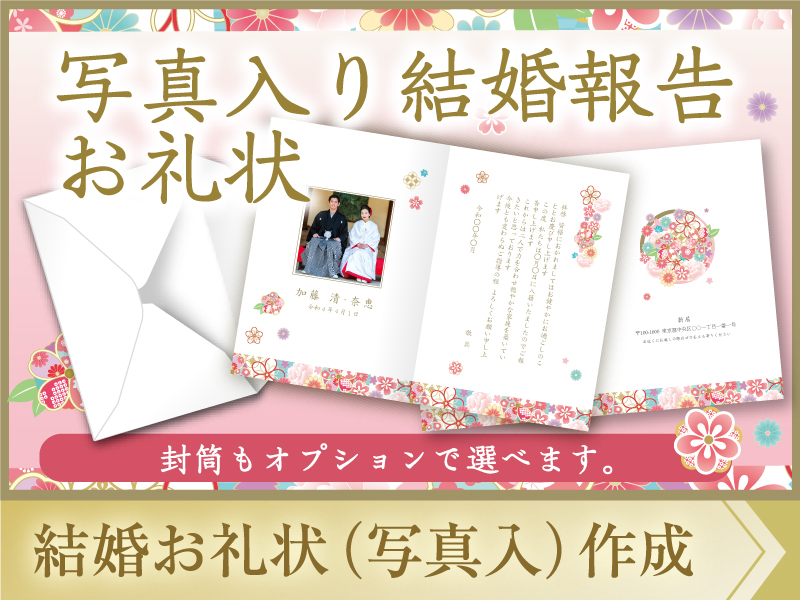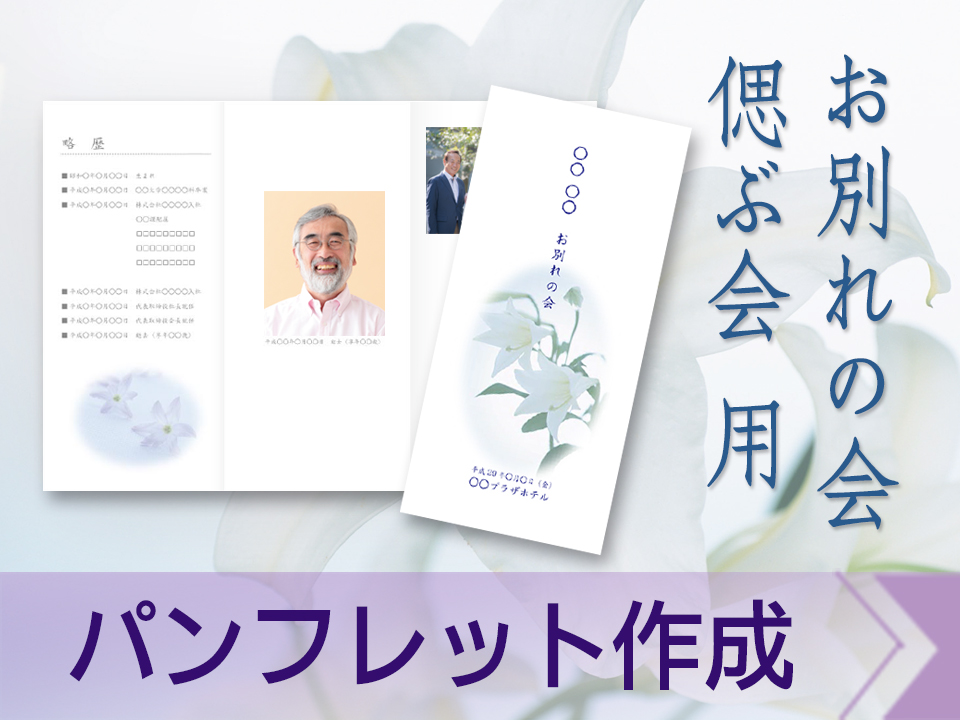死亡通知っていつ出すの?なんて書けばいいの?【挨拶状通販】

死亡通知とは、亡くなった方の家族や親族がその旨をお知らせすることです。
死亡通知はいつ送る?
死亡通知状は「はがき」や「封筒付きカード」などの書面で郵送します。
葬儀の前に出すか、後に出すかで通知状の目的と内容が変わってきます。
1. 葬儀の前に出す
誰がいつ亡くなり、その葬儀の日時・場所を伝える死亡通知
葬儀の前に出す通知状は、葬儀の日時や場所を伝えるためのものですが、一般的には、故人の親族や勤務先関係者、友人への連絡は電話で知らせます。社葬や会社関係の死亡通知では郵送でお知らせする場合がほとんどです。
2. 葬儀の後に出す
誰がいつ亡くなり、葬儀を無事終えたこと、故人に代わって生前お世話になったお礼を伝える死亡通知
故人と数回会った程度の人や、遠方に住んでいて交流が途絶えているような人には葬儀後にお知らせします。
葬儀を済ませた後に出す死亡通知状は、亡くなったことに加え、葬儀が無事終了したこと、故人に代わって生前お世話になったお礼を伝える大切な挨拶状となります。家族や近親者のみで葬儀を執り行った場合は、このような形で訃報を伝えることが多くなっています。
簡潔に内容を伝え、できるだけ早く送るようにし、通知が遅くなってしまったことをお詫びしましょう。
また、年末が近い頃であれば死亡通知を出すのではなく、喪中はがき(年賀状の欠礼はがき)でお知らせするという形でも問題ありません。
死亡通知はできるかぎり早く出す方が良いですが、ご家族のタイミングで出せるときに出しましょう。タイミングとしては、葬儀後、納骨後、四十九日後、このあたりに合わせると出しやすいかと思います。
ここでは主に葬儀後に出す死亡通知に関しての情報となります。
1. 死亡通知に書く内容
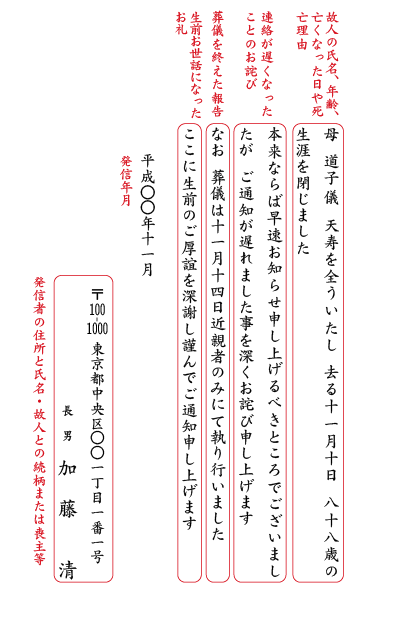
見本は死亡通知AC04になります。
こちらからご注文いただけます。
・喪主(発信者)との続柄、氏名
家族が喪主になる場合には、「名」だけでも構いません。姓の異なる喪主の場合はフルネーム「姓と名」を書きます。
・死亡日、年齢、死亡理由
死亡理由は無理に書く必要はありませんが、できれば亡くなった日付と年齢はお伝えしましょう。
・葬儀を終えた事
・連絡が遅くなったお詫び、生前のご厚情に対するお礼
・発信年月日
死亡通知状を出す年月です。基本的には書いた日や、葬儀や法要を行った日ではありません。
「○年○月」と日にちを入れなくても大丈夫です。
・喪主(又は発信者)の氏名と住所
・故人との続柄、または「喪主」
「喪主」や「妻」、「長男」など故人との関係
例えば、はじめに「夫 ○○」とすれば、必然的に差出人が「妻」とわかりますのでこの場合は必須ではありません。
2. 死亡通知の書き方
・時候の挨拶は不要
時候の挨拶は不要です。感情表現なども控えます。
・句読点は付けず、行頭を揃える
・薄墨について
薄墨には、「涙で墨が薄くなってしまった」という意味があります。
ですが、黒で書く(印刷)のは悲しくないとか、失礼ということではありませんので、薄墨にこだわらなくても大丈夫です。
薄いと読み手にとっては読みづらいこともあります。
・葬儀日程の案内を伝えなかった理由とお詫び
近年増えている親族のみで見送る家族葬などですと、故人と親しかった友人などからすれば知らぬ間に葬儀を終えていたということになります。後で知った事で気を悪くされないようにその理由をしっかりと記し、改めて故人への厚情に対してお礼を述べましょう。
・添え書き
香典や供物などを辞退したいという場合、その旨も死亡通知に記載しておきましょう。
3. 死亡通知を送る時期
葬儀の前に、葬儀の日時・場所などを知らせる死亡通知は、できるだけ早く出し、遅くとも葬儀の前日までに先方に届くようにします。
葬儀の後に出す死亡通知状は、一般的には初七日の頃とされていますが、それを過ぎてしまってもできるだけ早く出すようにしましょう。
4. 死亡通知は簡潔な内容で
故人に代わって、生前お世話になった方に状況を伝える挨拶状なので、内容は簡潔に、できるだけ早く送る事を心掛けましょう。そのため時候の挨拶は不要となります。
5. 死亡通知と喪中欠礼はどう違う
死亡通知は故人がなくなっとことを、故人と関係があった方(同居していない家族・近親者・知人・友人・仕事関係者など)に知らせる目的で送ります。差出人は喪主など代表者の名前で出します。
喪中欠礼は差出人の近親者に1年以内に不幸があり、喪に服していて慶事を避け「その年の年賀状は出しません」という事を、差出人の関係者に知らせる目的で送ります。差出人は本人の名前(又は夫婦連名)で出します。
6. 例文
例文1 葬儀後に出す死亡通知
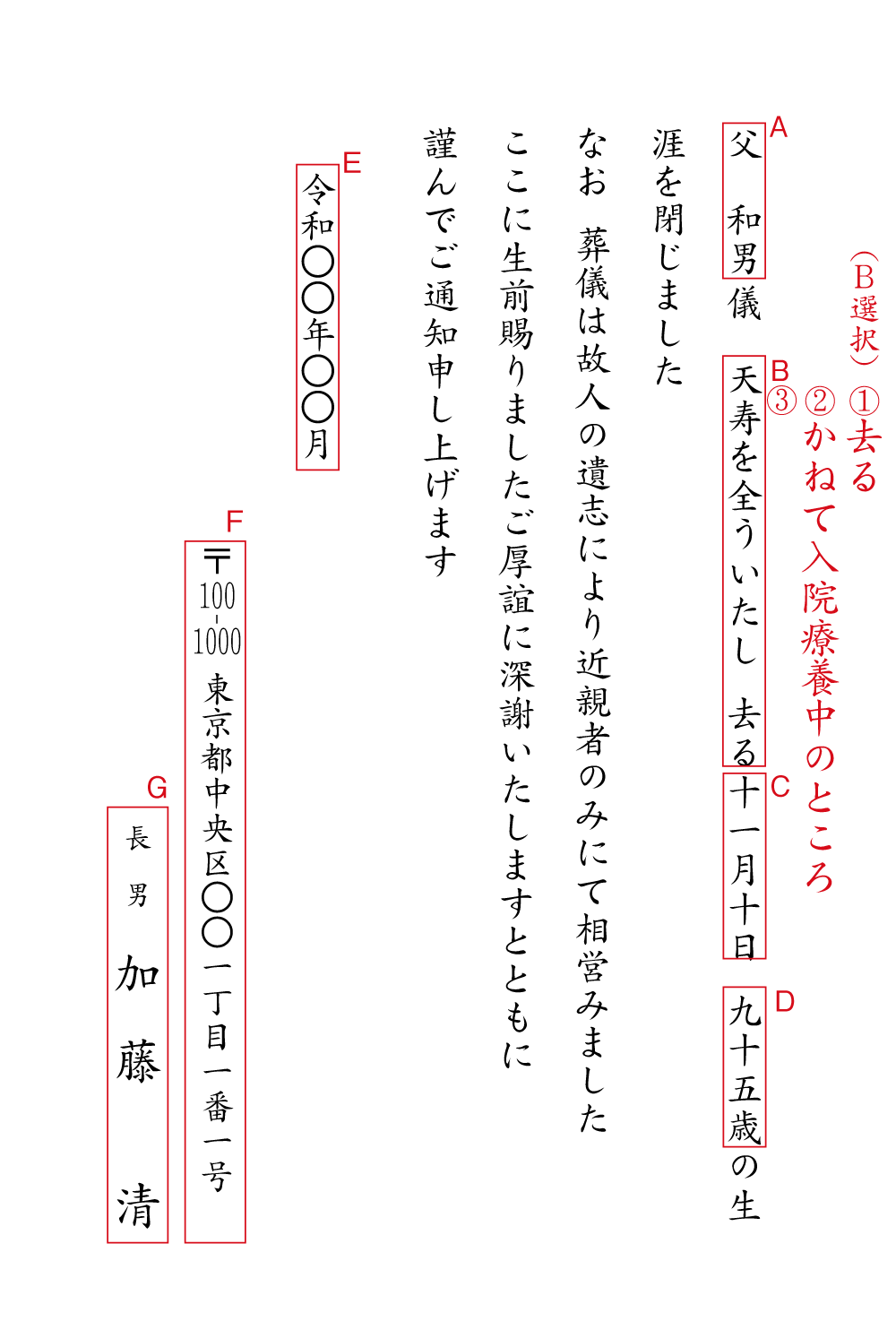
例文2 四十九日法要後に出す死亡通知
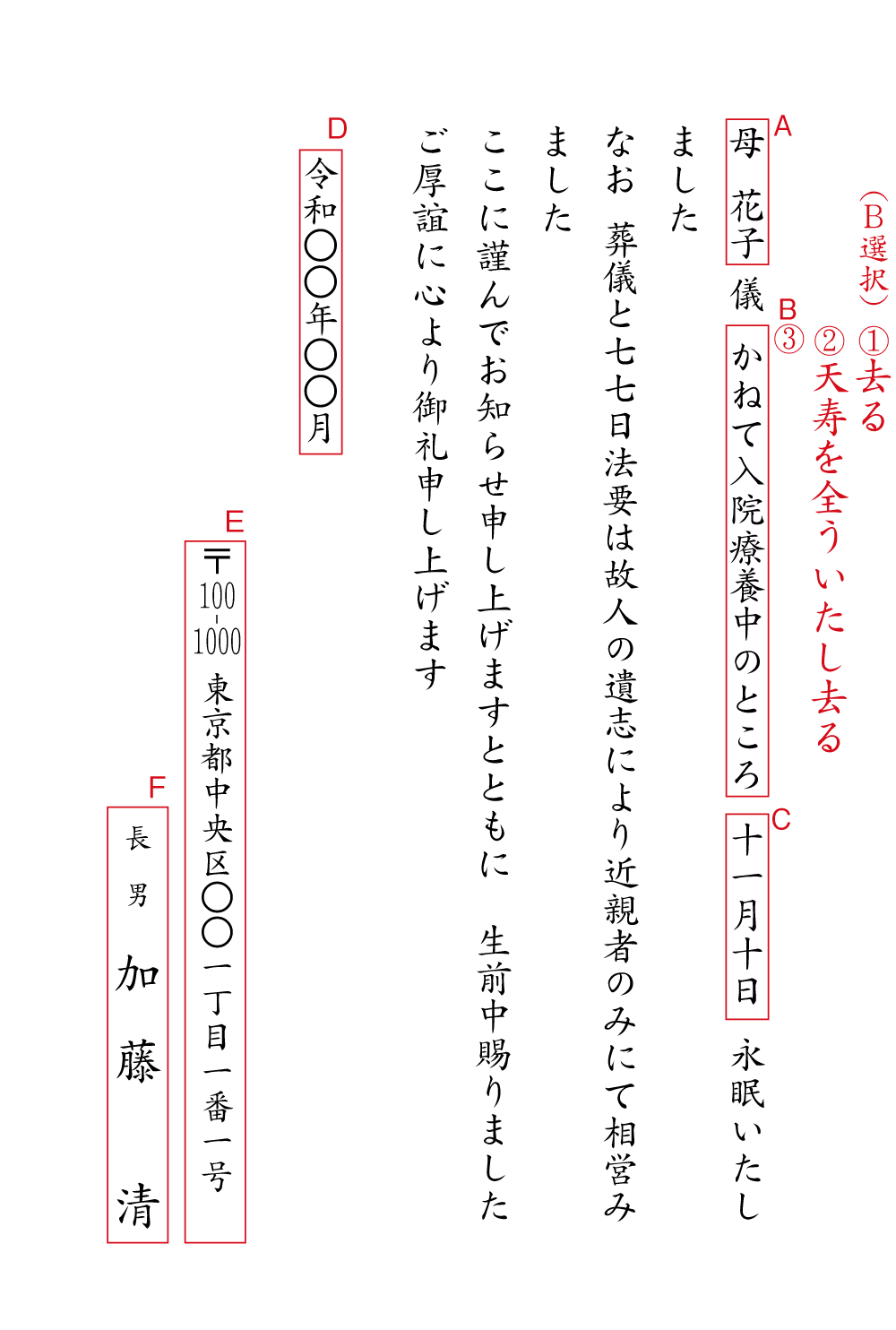
葬儀と四十九日法要の日付を入れるパターンもあります。